全国のインキュベーション施設

2024年3月29日
株式会社フレンドマイクローブ
微生物分解技術を活用し 低コストで環境に優しい 油処理サービスを実現

食品加工などの工場の排水に含まれる産業用油の廃棄処理は、これまでは排水から油を物理的に分離し、処理場に運んで焼却するなど、高コストで環境負荷のかかる方法が一般的でした。名古屋医工連携インキュベータに入居するフレンドマイクローブは、名古屋大学で開発された、油脂を効率的に分解する微生物の技術を活用することで、低コストで環境に優しい油処理サービスを実現します。その技術の特徴と将来展望について伺いました。(2023年12月取材)
インタビュー
お話 株式会社フレンドマイクローブ(名古屋医工連携インキュベータ入居)
代表取締役 蟹江 純一氏
起業、会社のおいたち

会社設立の経緯をお聞かせください
名古屋大学大学院工学研究科の堀克敏教授が微生物研究で開発した成果を、事業として社会に広く実装する目的で2017年に設立しました。企業との共同研究や、科学技術振興機構(JST)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の研究助成金を受け、最初のシーズとなる油脂分解技術を開発、油脂の生産工場での実証試験で正常に稼働できるまで技術を高めた上で起業しています。
「マイクローブ」というのは微生物を英語に訳したもので、社名は「微生物と友達(フレンド)に」という意味合いがあります。
もともとは堀教授の研究室の学生だったと聞いています
学生時代は油脂分解技術とは異なる微生物の研究をしていました。堀教授がバイオベンチャーの草分け的な会社を上場させた西田克彦氏を代表として一緒に会社を立ち上げたのですが、西田氏の年齢のこともあって次の代表を探す必要があり、私に声がかかりました。ちょうど私も研究室を出るタイミングであり、以前から会社経営にも関心があったことから、社長に就任する決意をしました。
事業の展開と現在
御社の技術は、どのような課題を解決するのでしょうか
私どもの油脂分解システム「MiBiocon(マイビオコン)-FW」は、食品加工工場などから出される排水に含まれる油脂を対象としています。従来は排水中の油脂を物理的に分離し、再利用性の低い産業廃棄物として処理されていました。当社では名古屋大学が開発した高性能な微生物群が油脂を分解する方法を採用することで、油性汚泥の発生を抑制し、油性廃棄物の削減、悪臭の解消、廃棄物処理コストの削減などの効果を提供しております。
さらに、油性廃棄物を処理する工程での石油燃料による焼却時に発生する温室効果ガスの排出量を減少させる効果も期待できます。廃棄物の再利用性の向上も目指しており、この技術を用いることで汚泥や生ゴミの再利用性を向上させ、肥料や飼料として活用できるようになります。

微生物を活用する点がこれまでと違うというわけですね
単に良い微生物を持ってきただけではうまくいきません。微生物をどのように適応させるか、その方法論がとても重要となります。微生物が高い性能を発揮させるための環境を整える、いわゆる化学工学の世界であり、環境微生物の実用化の分野でそこまで踏み込んでいる研究者はあまりいません。一方で、微生物の振る舞いは複雑で、経験則の部分もあります。まず微生物を適用できる現場を探すのですが、そのままでは適用できない現場でも最適な環境をアレンジできることが、われわれの強みと言えます。
なぜ、そのような特徴のある技術開発を実現できたのでしょうか
当社を立ち上げた堀教授は、微生物や酵素を利用した課題解決を目指す応用研究や、その基礎となる反応・作用機構の解明に取り組むなど、微生物関連の深い専門知識と研究成果を有しています。このような学術的基盤は、先進的な技術を開発する上で重要な役割を果たしています。当社はその技術基盤を応用した研究開発型ベンチャーであり、前述の微生物の環境を整える提案力にもつながっているというわけです。
そのほかにどのような技術を開発していますか
大きく二つあります。一つは、中小規模の工場や飲食店のテナントが入る建物から出た油を処理する技術です。そのようなところには、ただ流すだけで油を分離できるグリーストラップと呼ばれる設備が置かれています。これまでは、分離した油を定期的にバキュームカーで吸って処理していましたが、悪臭の発生源になったり、清掃しなければ油が流れ出て配管詰まりなどのトラブルの原因になったりもします。そこに当社の微生物によって油を分解処理する仕組みを取り入れます。
もう一つは、生ゴミなど固形廃棄物を処理する技術です。固形廃棄物に油脂があるとうまく堆肥にできないため、微生物の油脂分解により、堆肥加工率を上げることができます。
そしてこれから
将来展望について、どのようにお考えですか
適用範囲を動植物油だけでなく、鉱物油(機械系油)にも広げたいと考えています。特に愛知県は鉱物油を使う製造業者が多く存在するため、大きなビジネスチャンスととらえています。鉱物油の分解は文献自体も少なく、動植物油に比べて難易度は高いですが、チャレンジする価値があります。そのほか、協力企業との共同研究でカーボンナノチューブなど油脂以外の難分解性物質の分解にも取り組んでいます。将来的には、微生物反応による二酸化炭素の固定化システムの開発も手掛けていきます。
海外市場でも油処理のニーズはありそうですね
特に東南アジアでは油処理への意識がまだ高くないことから、当社の技術のメリットが理解されれば、一気に広まると期待しています。ただ、海外展開を考える場合、異なる環境規制、文化、市場ニーズなどに適応する必要があります。ローカルなパートナーシップの確立、現地の規制や文化に合わせた製品のカスタマイズを進めていきたいと考えています。
中小機構インキュベーションとの関わり
入居のきっかけ、入居してよかったこと
もともとは名古屋大学を拠点としていましたが、研究開発スペースが必要となり、探していた時に、イベントでチーフインキュベーションマネージャーにお会いし、施設で空きがあることを教えていただきました。前社長が別のベンチャーに関与していた頃に入居していた経験者だったこともあり、この施設の良さを知っていたので入居を決めました。
よかった点として、様々なサポートを受けられるというところが大きいと思います。最初に中小基盤整備機構の「FASTAR」を紹介され、1年がかりで支援していただきました。その後の多くの受賞や次のアクセラレーションプログラムにつながり、最終的に資金調達に至りました。商談できる来客スペースも活用させていただき、とても助かっています。
今後インキュベーション施設を利用する方へのメッセージ
多くの人に支えられているということを日頃から感じています。社内スタッフだけではどうしても限界があり、外部のいろいろなサポートを受けられる環境はベンチャーにとって必要です。特にこの施設では、会社が成長する最初のところで非常に価値のあるサポートが受けられることから、ぜひ活用していただければと思います。
会社情報
会社名 |
|
|---|---|
代表取締役 |
蟹江 純一 |
所在地 |
愛知県名古屋市千種区千種二丁目22番8号 |
事業概要 |
油分解微生物の製造・販売、新規微生物ビジネスの開拓 |
会社略歴
2017年6月 |
株式会社フレンドマイクローブを設立 |
|---|---|
2017年10月 |
名古屋大学発ベンチャーの認定を受ける |
2021年5月 |
代表取締役社長に蟹江純一が就任 |
2021年11月 |
2021年度中小企業基盤整備機構主催「FASTAR(第5期)」に採択 |
2022年7月 |
特許庁の知財アクセラレーションプログラム「IPAS2022」に採択 |
2022年10月 |
「CNBベンチャー大賞 2022」にて中部経済産業局長賞を受賞 |
2023年1月 |
「愛知環境賞」にて名古屋市長賞を受賞 |
2023年5月 |
第三者割当増資にて総額2億3000万円の資金調達を実施 |
2023年12月 |
名古屋大学、日本ゼオンとの共同研究成果をプレスリリース |
担当マネージャーからのコメント
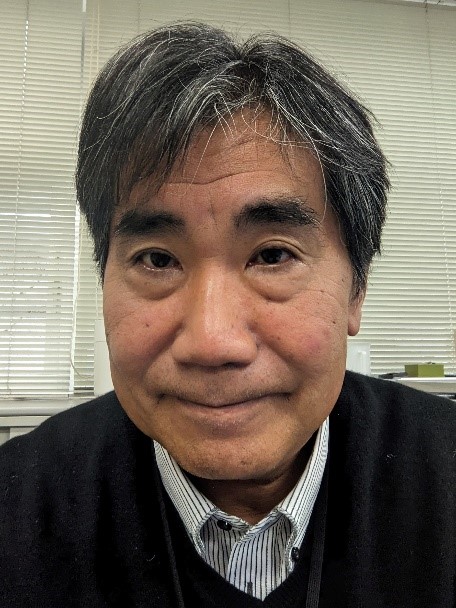
フレンドマイクローブは、環境微生物による汚水処理という「SDGs(持続可能な開発目標)」に取り組む名古屋大学発ベンチャーです。蟹江 純一社長は、大学卒業時に内定していた大企業への就職を選択せず、ベンチャーにチャレンジした勇気ある研究者です。社長に就任直後、財務・総務といった経営面を学びたいという相談をいただき、アクセラレーションプログラム「FASTAR(第5期)」の応募を推薦し、採択されました。期間内のメンタリングに同席して共に学び、成長を感じることができたのが楽しい思い出です。
「FASTAR 5th DEMODAY」以降、様々なピッチで受賞を重ね、2023年度には事業拠点も確保しました。次のステージへと進まれた蟹江社長を送り出す日を楽しみに、インキュベーションマネージャー(IM)一同が日々、コミュニケーションを重ねています。