- Home
- 職員インタビュー [創業・ベンチャー支援部創業・ベンチャー支援企画課] 大場 孝典
職員インタビュー
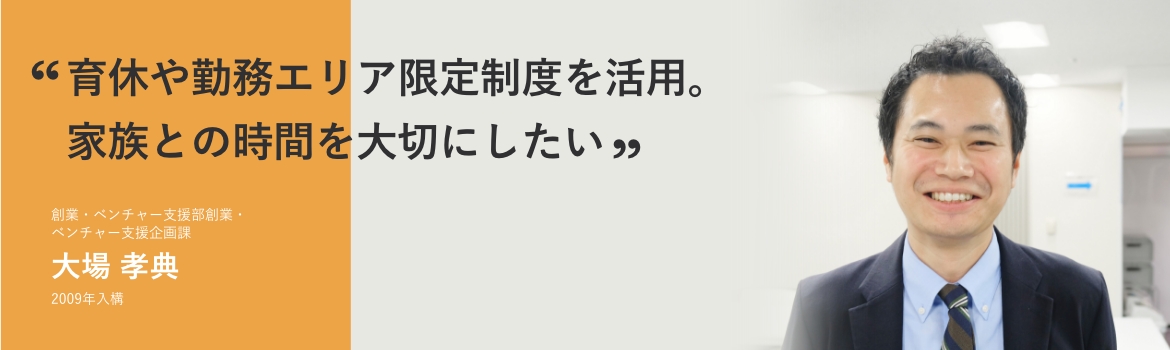
中小機構では、男性の育休取得者が増えています。大場さんは地域本部からの異動直後に育児休暇を取得しました。育休前は「仕事を離れることへの不安があった」という大場さんに話を聞きました。
金融機関から中小機構へ転職
東京都出身で、大学は商学部に進学しました。就職活動では、様々な業種を見て回りましたが、家族全員が金融機関に勤めていたこともあり、最も身近な業界であった銀行に就職しました。窓口業務の他、法人・個人向け融資の営業や資産運用の提案を担当しました。勤めていた銀行は東京近郊での勤務に限られていましたが、東京以外の地域でも中小企業支援の仕事をしたいと思っていました。そんな時、中小機構の社会人採用の募集を見つけ、ここでなら全国各地で多様な業種の中小企業と関わることができると考え、転職を決意しました。
2009年の2月に入構し、最初に経理課へ配属されました。経理課では、主に機構の決算書作成を担当しました。2014年から出向した関東経済産業局では経済産業政策の普及活動等の業務を、その後、高度化事業部で貸付金回収の管理業務と、企画部での補助金業務を経験し、2022年に中部本部へ異動しました。中部本部では企業への事業スペースの貸出や専門家による経営支援を提供するインキュベーション事業を担当しました。
中部本部所管のインキュベーション施設は3施設あり、企業の入居審査や、入居企業に対するサポートなどを担当していました。また、国が「スタートアップ育成5か年計画」を決定してからは、スタートアップ支援も担当しました。自分より若い経営者の方々も多く、そうした方々のチャレンジする姿勢を間近で見て、私も大きな刺激を受けました。
子どもの成長が間近で見られた育休期間

2024年7月から本部に戻り、創業・ベンチャー支援部で働いています。ここでは、全国のインキュベーション事業やスタートアップ支援事業の総括業務や起業家の表彰制度であるJapan Venture Awardsを担当しています。異動した翌月に、1か月の育児休業を取得しました。機構内でも、男性職員の育休取得が増えてきています。異動したばかりで不安はありましたが、中部本部にいた時から人事課に育休取得の意向を伝え、異動が決まった時点で配属先の上司にも伝えていたので、スムーズに取ることができました。
育休中は、上の子ども達の育児や料理、洗濯等をしていました。中部本部時代は単身赴任していたので、当時、妻が一人で全てをやっていたのかと思うとその大変さを実感しましたし、改めて「ありがとう」という想いを持ちました。仕事復帰前は、「もっと子ども達と一緒にいたい」という気持ちと「早く戻らないと仕事から取り残されてしまうのでは」という焦りがありましたが、上司から業務の進捗状況を連絡していただいたため、育休後の復帰は予想以上に順調でした。課長をはじめ、フォローしていただいた部・課の方々には、感謝の気持ちでいっぱいです。
単身赴任で2年間離れていたこともあり、子どもと多くの時間を過ごせたことも含め、育休には大きな意味があったと感じています。「男性だから」という理由で取得しづらい空気もありませんでした。もし育児休暇の取得を希望する職員から相談されたら、ぜひ取得するように勧めたいです。昨年からは、一定期間、勤務エリアを固定できる「勤務エリア限定制度」も利用しています。子どもはいくつになっても心配事が尽きないので、家族の近くにいられるこの制度は、今の自分のライフステージに合っていると感じます。
機構には民間企業にない良さがある

ここ数年スタートアップ支援の業務を続けて経験し、起業家の方々が一生懸命チャレンジしている姿勢に触れてきました。その経験から、機構として何か力になれるようなことをしたいと考えるようになり、今後もスタートアップ支援に関わりたいと思うようになりました。
機構は業務の幅が広いので、どんな学部出身の方でも、活躍できるフィールドが拡がっています。異動の度に転職したような気持ちになりますが、色々な立場の方と接する機会も多く、新たな学びを得続けることができます。興味があればぜひ応募していただきたいです。
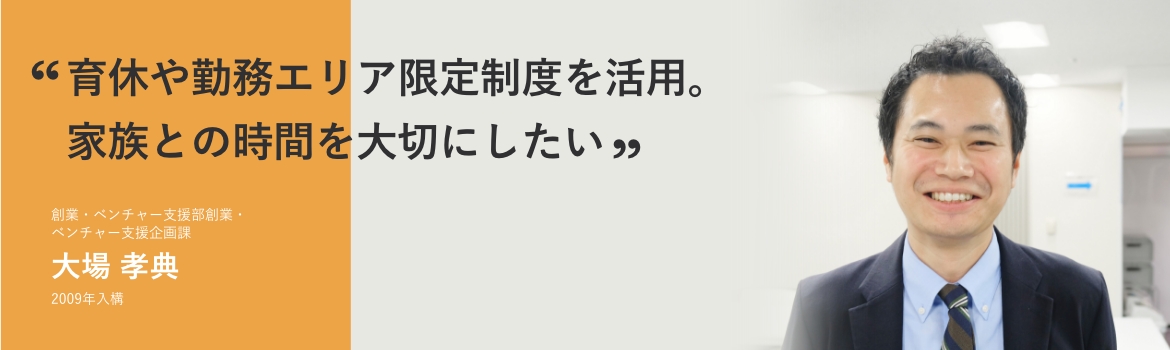
中小機構では、男性の育休取得者が増えています。大場さんは地域本部からの異動直後に育児休暇を取得しました。育休前は「仕事を離れることへの不安があった」という大場さんに話を聞きました。
金融機関から中小機構へ転職
東京都出身で、大学は商学部に進学しました。就職活動では、様々な業種を見て回りましたが、家族全員が金融機関に勤めていたこともあり、最も身近な業界であった銀行に就職しました。窓口業務の他、法人・個人向け融資の営業や資産運用の提案を担当しました。勤めていた銀行は東京近郊での勤務に限られていましたが、東京以外の地域でも中小企業支援の仕事をしたいと思っていました。そんな時、中小機構の社会人採用の募集を見つけ、ここでなら全国各地で多様な業種の中小企業と関わることができると考え、転職を決意しました。
2009年の2月に入構し、最初に経理課へ配属されました。経理課では、主に機構の決算書作成を担当しました。2014年から出向した関東経済産業局では経済産業政策の普及活動等の業務を、その後、高度化事業部で貸付金回収の管理業務と、企画部での補助金業務を経験し、2022年に中部本部へ異動しました。中部本部では企業への事業スペースの貸出や専門家による経営支援を提供するインキュベーション事業を担当しました。
中部本部所管のインキュベーション施設は3施設あり、企業の入居審査や、入居企業に対するサポートなどを担当していました。また、国が「スタートアップ育成5か年計画」を決定してからは、スタートアップ支援も担当しました。自分より若い経営者の方々も多く、そうした方々のチャレンジする姿勢を間近で見て、私も大きな刺激を受けました。
子どもの成長が間近で見られた育休期間

2024年7月から本部に戻り、創業・ベンチャー支援部で働いています。ここでは、全国のインキュベーション事業やスタートアップ支援事業の総括業務や起業家の表彰制度であるJapan Venture Awardsを担当しています。異動した翌月に、1か月の育児休業を取得しました。機構内でも、男性職員の育休取得が増えてきています。異動したばかりで不安はありましたが、中部本部にいた時から人事課に育休取得の意向を伝え、異動が決まった時点で配属先の上司にも伝えていたので、スムーズに取ることができました。
育休中は、上の子ども達の育児や料理、洗濯等をしていました。中部本部時代は単身赴任していたので、当時、妻が一人で全てをやっていたのかと思うとその大変さを実感しましたし、改めて「ありがとう」という想いを持ちました。仕事復帰前は、「もっと子ども達と一緒にいたい」という気持ちと「早く戻らないと仕事から取り残されてしまうのでは」という焦りがありましたが、上司から業務の進捗状況を連絡していただいたため、育休後の復帰は予想以上に順調でした。課長をはじめ、フォローしていただいた部・課の方々には、感謝の気持ちでいっぱいです。
単身赴任で2年間離れていたこともあり、子どもと多くの時間を過ごせたことも含め、育休には大きな意味があったと感じています。「男性だから」という理由で取得しづらい空気もありませんでした。もし育児休暇の取得を希望する職員から相談されたら、ぜひ取得するように勧めたいです。昨年からは、一定期間、勤務エリアを固定できる「勤務エリア限定制度」も利用しています。子どもはいくつになっても心配事が尽きないので、家族の近くにいられるこの制度は、今の自分のライフステージに合っていると感じます。
機構には民間企業にない良さがある

ここ数年スタートアップ支援の業務を続けて経験し、起業家の方々が一生懸命チャレンジしている姿勢に触れてきました。その経験から、機構として何か力になれるようなことをしたいと考えるようになり、今後もスタートアップ支援に関わりたいと思うようになりました。
機構は業務の幅が広いので、どんな学部出身の方でも、活躍できるフィールドが拡がっています。異動の度に転職したような気持ちになりますが、色々な立場の方と接する機会も多く、新たな学びを得続けることができます。興味があればぜひ応募していただきたいです。
