- Home
- 本部と地域本部でチームを結成。能登半島地震の復興支援の現場で

2024年1月1日、石川県能登地方を震源とするM7.6の能登半島地震が発生し、甚大な被害をもたらしました。震度7を観測した輪島市では、日本三大朝市の一つ「輪島朝市」が地震に伴う火災により全焼。中小機構は地震直後から被災地の状況確認と情報収集を実施しました。その後、朝市側からの支援依頼を受け、「輪島朝市の特徴を活かした施設整備構想検討会」の運営をサポートしました。今回は、輪島朝市の復興支援に取り組んだ北陸本部の早川さん、宮本さん、本部の北村さんに話を聞きました。(取材日:2024年11月15日)
全国から復興支援アドバイザーを派遣
ーー初めに、中小機構に入った経緯を教えてください。
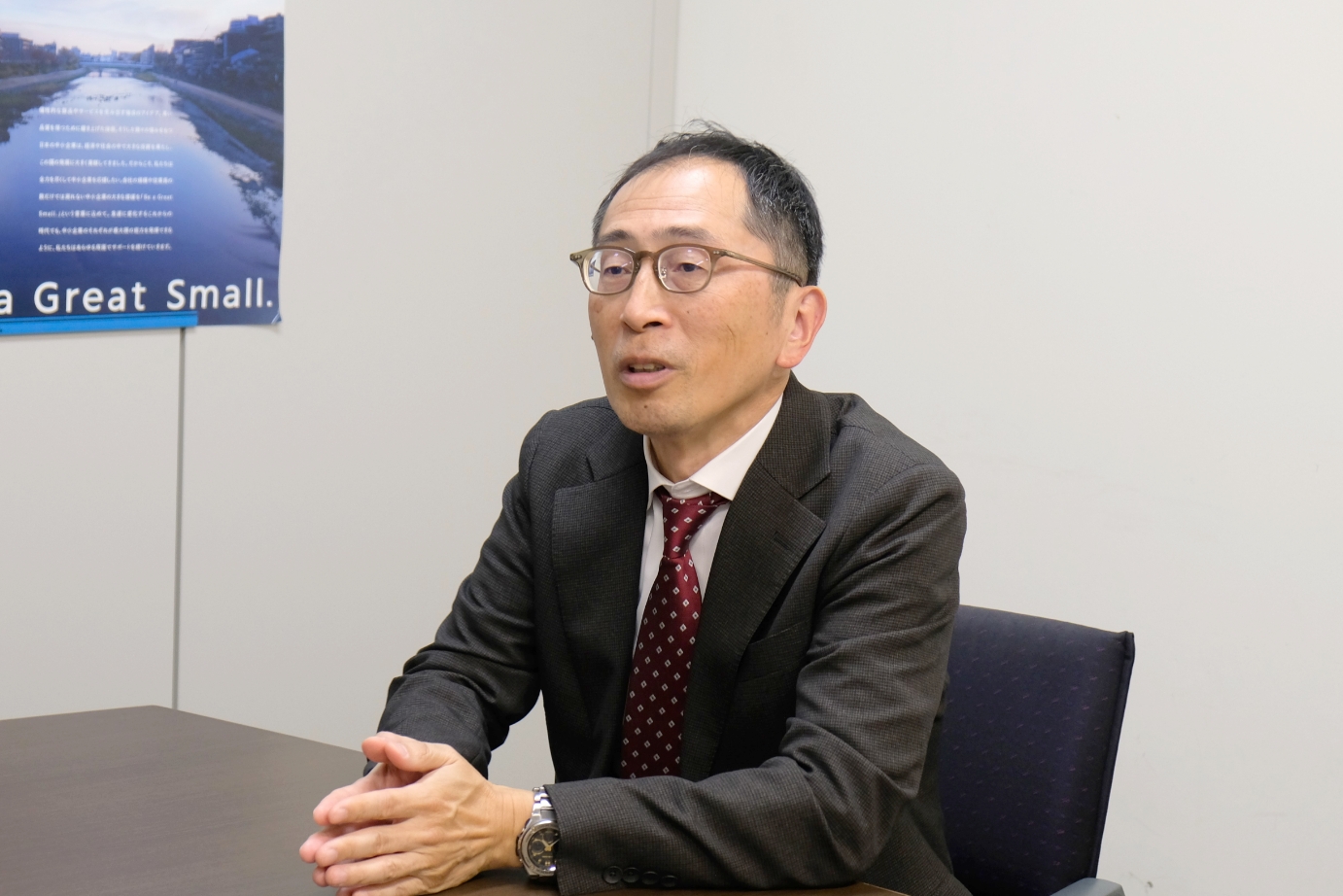
ーー中小機構が行う災害復興支援とは、どのようなものですか。
ーー能登半島地震の前に、災害復興支援の経験はありますか。
輪島朝市の復興構想案をサポート

ーー中小機構が支援を行った「輪島朝市の特徴を活かした施設整備構想検討会」とは、どのようなものでしょうか。

復興の主役はあくまで事業者
ーー復興支援の中で印象に残っていることを教えてください。

ーー復興支援の難しさを教えてください。
ーー最後に、入構希望者へメッセージをお願いします。

