- Home
- 職員インタビュー [関東本部東京校] 河野 広夢
職員インタビュー
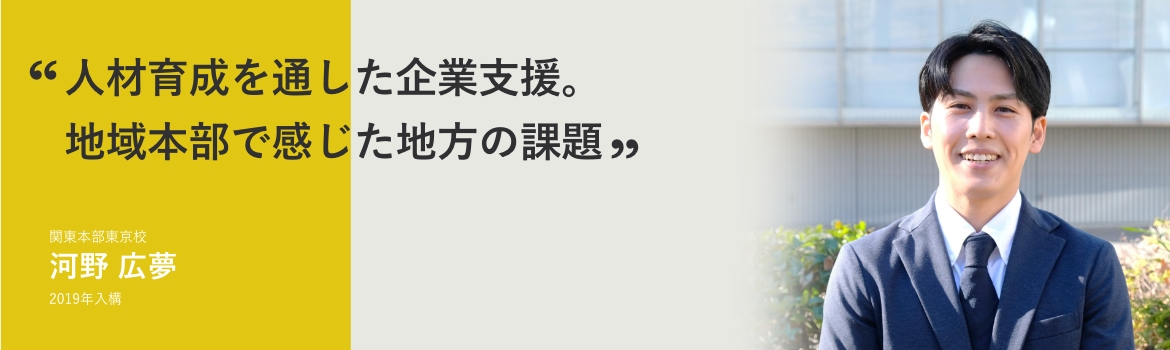
河野さんは、四国本部で企業向け人材育成の研修業務を担当し、現在は中小企業大学校東京校で引き続き研修の運営に携わっています。中小機構の人材育成事業が企業にどのように貢献しているか、話を聞きました。
コロナ禍、手探りで進めた国際支援
徳島県出身で、大分の大学の国際経営学部に進学しました。学生時代を過ごした別府市は、様々な国籍の方が暮らすグローバルな町でした。世界各地から集まってきた個性豊かな人々との出会いは、とても刺激的で面白い経験でした。卒業後、大阪の大学院へ進学しました。経営学研究科で、アカデミックな視点から中小企業論を学びました。中小機構の存在は大学院で知りました。国の機関として総合的な支援を行っているところに魅力を感じ、2019年に入構しました。
最初は国際交流センター国際交流課に配属されました。ここは海外の関係機関とのネットワーク構築を行う部署です。当時、担当していたのがサウジアラビアの中小企業育成事業だったのですが、コロナ禍が始まり、現地への渡航が困難になってしまいました。そのため、専門家の講義動画を撮影し、それを翻訳して現地に提供する、Eラーニング事業を始めました。中小機構でも前例がない取り組みで、すべてが手探り状態でした。講義内容の原稿を作成し、スタジオを借りて撮影、翻訳された英訳原稿の確認まで行いました。専門用語が多く苦労しましたが、大学院時代に多数の企業を訪問した経験が役に立ちました。

人材育成で企業の課題を解決したい
2021年、四国本部に異動しました。この2年間は管理部門で、総務、人事、財務など幅広い業務を担当しました。2023年からは、人材支援部で勤務しました。中小企業へ研修を行う中小企業大学校・四国キャンパスが、2019年に新設されたのですが、自前の研修施設を持っていないため、四国4県の貸し会議室を借りて研修を実施していました。四国全県をまわり、事業者と直接関わる中で、様々な生の声を聞くことができました。地方では人手不足が深刻で、人材育成に課題を抱えている事業者が多いです。特に若手が都心に流出してしまうため、地方企業における人材育成が大きな課題となっています。その課題解決の大きな支援策として、研修業務を実施することができ、やりがいを感じました。
2024年から、中小企業大学校・東京校に異動しました。東京校は60年以上の歴史があり、研修施設に加えて寮や読書室などもある、規模の大きい学校です。初めの3か月は、企業向けの民間研修を担当していました。9月からは「中小企業診断士」という国家資格を取得するための、養成課程を運営しています。受講生は支援機関の職員が中心です。研修は演習と実習で構成され、6か月間にわたってほぼ毎日実施しています。私は講師や受講生への対応、研修の企画やモニタリング、実習先企業の開拓・管理など、より良い研修環境の提供を目指し研修運営を行っています。

中小企業大学校・東京校の研修室
研修は有料で提供するサービスなので、プレッシャーもあります。単に楽しい研修ではなく、企業の方々が職場に戻って実践できる、実務に活かせる内容にするため、様々な工夫を重ねています。受講生に気づきを与え、自社の課題解決に取り組んでもらうことが私たちの役目だと思っています。
人間力が鍛えられる仕事

もともと人材育成よりも学生時代に研究していた事業承継に興味があったのですが、四国本部での経験を通じて、人への関心が深まりました。現在の業務では講師や受講生など、人との関わりがたくさんあり、人間力が鍛えられています。人材育成の仕事を通して、企業の成長を見届けられることにもやりがいを感じています。
中小機構の魅力は、総合的な支援を日本全国で展開できることです。地域に密着したサポートから、より広い視野での支援まで、様々な事業があります。事業が幅広い分、部署が変われば、全く新しいことに挑戦する場面にたくさん出会います。何事も初めてのことは不安に感じますが、まずは、やってみるの姿勢で取り組める知的探究心が強い人に、ぜひ来てほしいです。
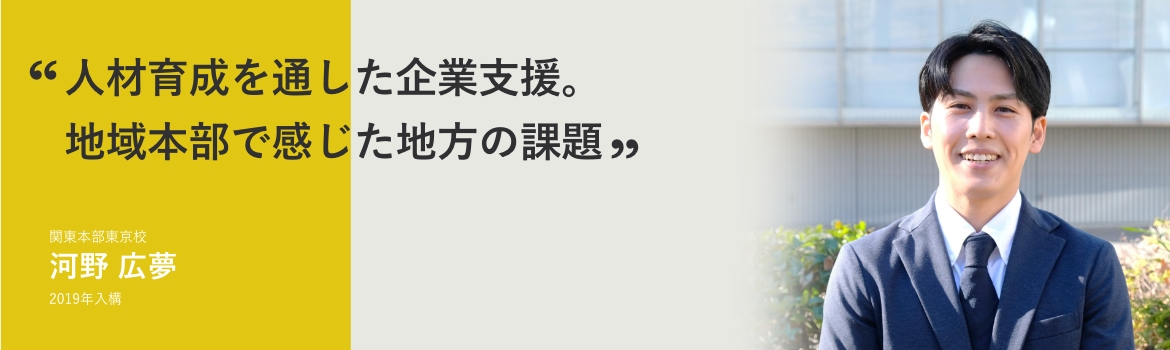
河野さんは、四国本部で企業向け人材育成の研修業務を担当し、現在は中小企業大学校東京校で引き続き研修の運営に携わっています。中小機構の人材育成事業が企業にどのように貢献しているか、話を聞きました。
コロナ禍、手探りで進めた国際支援
徳島県出身で、大分の大学の国際経営学部に進学しました。学生時代を過ごした別府市は、様々な国籍の方が暮らすグローバルな町でした。世界各地から集まってきた個性豊かな人々との出会いは、とても刺激的で面白い経験でした。卒業後、大阪の大学院へ進学しました。経営学研究科で、アカデミックな視点から中小企業論を学びました。中小機構の存在は大学院で知りました。国の機関として総合的な支援を行っているところに魅力を感じ、2019年に入構しました。
最初は国際交流センター国際交流課に配属されました。ここは海外の関係機関とのネットワーク構築を行う部署です。当時、担当していたのがサウジアラビアの中小企業育成事業だったのですが、コロナ禍が始まり、現地への渡航が困難になってしまいました。そのため、専門家の講義動画を撮影し、それを翻訳して現地に提供する、Eラーニング事業を始めました。中小機構でも前例がない取り組みで、すべてが手探り状態でした。講義内容の原稿を作成し、スタジオを借りて撮影、翻訳された英訳原稿の確認まで行いました。専門用語が多く苦労しましたが、大学院時代に多数の企業を訪問した経験が役に立ちました。

人材育成で企業の課題を解決したい
2021年、四国本部に異動しました。この2年間は管理部門で、総務、人事、財務など幅広い業務を担当しました。2023年からは、人材支援部で勤務しました。中小企業へ研修を行う中小企業大学校・四国キャンパスが、2019年に新設されたのですが、自前の研修施設を持っていないため、四国4県の貸し会議室を借りて研修を実施していました。四国全県をまわり、事業者と直接関わる中で、様々な生の声を聞くことができました。地方では人手不足が深刻で、人材育成に課題を抱えている事業者が多いです。特に若手が都心に流出してしまうため、地方企業における人材育成が大きな課題となっています。その課題解決の大きな支援策として、研修業務を実施することができ、やりがいを感じました。
2024年から、中小企業大学校・東京校に異動しました。東京校は60年以上の歴史があり、研修施設に加えて寮や読書室などもある、規模の大きい学校です。初めの3か月は、企業向けの民間研修を担当していました。9月からは「中小企業診断士」という国家資格を取得するための、養成課程を運営しています。受講生は支援機関の職員が中心です。研修は演習と実習で構成され、6か月間にわたってほぼ毎日実施しています。私は講師や受講生への対応、研修の企画やモニタリング、実習先企業の開拓・管理など、より良い研修環境の提供を目指し研修運営を行っています。

研修は有料で提供するサービスなので、プレッシャーもあります。単に楽しい研修ではなく、企業の方々が職場に戻って実践できる、実務に活かせる内容にするため、様々な工夫を重ねています。受講生に気づきを与え、自社の課題解決に取り組んでもらうことが私たちの役目だと思っています。
人間力が鍛えられる仕事

もともと人材育成よりも学生時代に研究していた事業承継に興味があったのですが、四国本部での経験を通じて、人への関心が深まりました。現在の業務では講師や受講生など、人との関わりがたくさんあり、人間力が鍛えられています。人材育成の仕事を通して、企業の成長を見届けられることにもやりがいを感じています。
中小機構の魅力は、総合的な支援を日本全国で展開できることです。地域に密着したサポートから、より広い視野での支援まで、様々な事業があります。事業が幅広い分、部署が変われば、全く新しいことに挑戦する場面にたくさん出会います。何事も初めてのことは不安に感じますが、まずは、やってみるの姿勢で取り組める知的探究心が強い人に、ぜひ来てほしいです。
